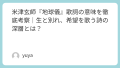1. 社会・業界の不条理に苦悩する“主人公像”
『RED OUT』の歌詞において象徴的に登場する「スネーク」や「プレジデント」、そして「泣いている少年」などのキャラクターたちは、米津玄師が感じる社会や音楽業界への違和感を反映していると読み取れます。スネーク(蛇)は古来より欺瞞や裏切りの象徴であり、プレジデント(大統領)は権力者や支配層を連想させます。
特に「今泣いてるのは誰?」という問いかけは、被害者であるはずの少年の涙にフォーカスを当てながら、その背景にある構造的な暴力や搾取に対する怒りを浮かび上がらせています。米津はこの曲を通じて、単なる社会批判に留まらず、業界内外における“見えない暴力”に声を上げているのです。
2. 創作そのものがもたらす“痛みと葛藤”
歌詞中に登場する「破傷風」「グロインペイン」といった医学的・生理的な用語は、米津自身が抱える創作上の苦しみをリアルに表現しています。破傷風は傷から感染する強い痛みのある病気、グロインペインは股関節の炎症によるスポーツ障害を意味します。これらは比喩的に、創作活動における限界への挑戦と、それに伴う精神的・肉体的なダメージを象徴しています。
彼の過去作でも「表現すること=自傷的行為」というテーマが繰り返し現れていましたが、『RED OUT』ではそれがさらに先鋭化され、聞き手に“表現者の痛み”を強く突き付ける構成となっています。
3. 専門用語(マクガフィン・デマゴギー等)の深読み
「マクガフィン」は映画・物語における物語推進のための“意味のない動機”を指す言葉であり、アルフレッド・ヒッチコックが広めた概念です。ここで米津は、自身の創作意欲や名声・目的といったものが“マクガフィン化”してしまったという空虚さを示唆している可能性があります。
また、「デマゴギー」は煽動政治を意味し、虚実が交錯する現代の情報社会やSNS環境への皮肉とも取れます。これらの専門用語をあえて選び歌詞に織り込むことで、米津は現代のコミュニケーションの曖昧さ、そして自己存在への疑念を詩的に描写しているのです。
4. 「RED OUT」という言葉が示す“極限状態”
タイトルにもなっている「RED OUT(レッドアウト)」とは、航空パイロットが急降下や加速時に血流が頭部から引き下がり視界が赤く染まる現象を指します。これは「限界状態」や「制御不能なスピード」「耐え難い重圧」を象徴する用語であり、歌詞の随所に散りばめられた疾走感や緊迫感と呼応しています。
「止まりたいのに止まれない」「走り続けなければいけない」といった心理状態は、現代を生きる表現者にとっての宿命ともいえる苦悩を表しており、米津玄師自身が音楽活動を通じて経験してきた“逃げ場のない衝動”が反映されているのです。
5. MV・ビジュアル演出に込められた“ホラー性と内省”
『RED OUT』のミュージックビデオでは、赤いストロボ、うさぎの仮面、歪んだ建物、そして激しく踊るシーンなど、ホラー的かつ内省的な演出が際立っています。これらのビジュアルは、歌詞の暗示する「極限状態」「混乱」「自我の分裂」などを補完し、視覚的にも強烈なメッセージを放っています。
特に赤い光は「RED OUT」の象徴であり、視覚を奪う恐怖と同時に、何か重大なものを見つめさせられる強制力を持っています。また、うさぎの仮面はアイデンティティの喪失や匿名性、逃避を意味するとも解釈でき、歌詞の持つ主題と深くリンクしていることが伺えます。
まとめ
『RED OUT』は単なる楽曲ではなく、米津玄師が抱える創作上の痛み、社会への不信、表現の限界といった多層的なテーマを、歌詞・音・映像のすべてを用いて伝えようとする“現代詩”のような作品です。専門用語や強烈なメタファーが散りばめられた本作は、深く読み解くほどに彼の内面世界と、私たちが生きる不条理な現実を照射してくれます。